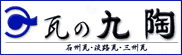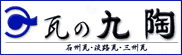5.瓦について
瓦の語源
広辞苑によれば、「瓦」とは「粘土を一定の形に固めて焼いたもの」と掲載されていますが、実際には粘土製瓦以外にも多くの材料の瓦があります。現在では屋根材と瓦は同じ意味で扱われています。
「かわら」の語源についてですが、サンスクリット語の物を覆う意味「カハラア」から転訛したものというのが一般的な説で、他に「屋根の皮」の意味とも、甲冑の古名の「カハラ」から出たとも言われています。
文献的に588年(約1400年前)に百済(現在の韓国の一部)が4人の瓦博士を献上したと日本書紀などに記述されており、日本国の瓦生産の 歴史が始まったようです。
|
瓦の形状
江戸時代までは本葺形と和形しかなく、明治以降に住宅の洋風化により、洋風タイプの瓦が多く商品化されるようになりました。
社寺建築にみられる本葺形は日本固有の粘土瓦のモデルです。本葺形は平瓦と丸瓦を組み合わせて葺くもので、最近では本瓦葺きの手間を省力化させる一体成形品もあります。
最近の、粘土瓦を代表する形と言えば、J形(和形)です。右または左に桟の重なりをつくり、前後に切り込みにより重ねをつくる我が国独自の形状で、江戸時代に考案されました。 |
粘土瓦の種類
粘土瓦は区分として釉薬瓦、いぶし瓦、無釉瓦に分類され、釉薬瓦は塩焼瓦を含みます。また、形状による区分、寸法による区分も設けていますが、メーカーによって特徴が異なるので、注意が必要です。
釉薬瓦は乾燥工程後、ガラス質のうわ薬で釉薬を施してから焼成して出来上がります。釉薬瓦の焼成は、燃えるための空気がある酸化雰囲気で行われます。生釉を使った釉薬瓦の場合は空気を遮断して、空気比1:1未満の還元雰囲気が必要になります。これは還元瓦と呼称しています。
また釉薬の代わりに食塩を用いたものは塩焼瓦といいます。
いぶし瓦は釉薬を使わず、焼成したあとに空気を完全に遮断、「むし炊き」にする燻化工程が特徴です。LPGなどで素地表面に銀色の炭素膜を形成させます。
釉薬を用いない素焼きや、金属酸化物を原料に練り込んだもの、窯内の雰囲気を酸化、還元などのコントロールで独特の窯変色を出す瓦は、いぶし瓦と同じ無釉系でも燻化工程がなく、無釉瓦と呼ばれます。 |
|
|